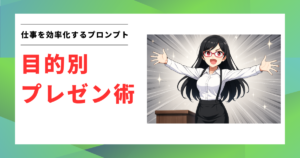はじめに
「採用したものの現場となじまなかった」「期待したスキルと違った」
こんな“よくあるミスマッチ”に悩んだ経験は、多くの方に心当たりがあるのではないでしょうか。
感覚頼みの面接から一歩抜け出し、AIを“壁打ち相手”として使うことで、採用の精度は驚くほど高まります。
この記事では、明日からすぐに実践できる具体的なテクニックをお伝えしていきます。
AIという心強いパートナーとともに、自社の未来を担う人材を見つけていきましょう。
1. 面接準備を加速させるプロンプト20選
ここからは、コピペしてすぐ使えるプロンプトを一挙に紹介します。
採用プロセスを「要件定義」「スキル確認」「カルチャーフィット」「ポテンシャル評価」の4段階に分け、それぞれのシーンでAIにどんな指示を出せばいいのかを明確にしました。
1-1. 採用要件とペルソナの明確化

まずは「どんな人を採るのか」をクリアにするところから始めましょう。
No.1 求める人物像の言語化
- 目的: 曖昧な要望を、具体的なペルソナ像へと落とし込む。
1. ロール設定
あなたは人事採用の専門家です。
2. 指示内容
以下の「募集背景」と「必須スキル」を踏まえ、具体的な候補者の「ペルソナ(人物像)」を3パターン作成してください。
それぞれのパターンについて、仕事へのモチベーションの源泉も推測してください。
3. 入力内容の例
・募集背景:新規事業の立ち上げメンバー。スピード感重視。
・必須スキル:法人営業経験3年以上、基本的なPCスキル。No.2 募集要項からの評価基準作成
- 目的: 募集要項(JD)をもとに、面接で見るべき基準を体系化する。
1. ロール設定
あなたは採用コンサルタントです。
2. 指示内容
以下の「募集要項」を分析し、面接官が確認すべき「5つの評価基準」を定義してください。
各基準について、5段階評価の定義(1が最低、5が最高)も作成してください。
3. 入力内容の例
・募集要項:[実際のJDを貼り付け]No.3 隠れた必須スキルの洗い出し
- 目的: 現場では言語化されにくい“暗黙の必須スキル”を見つける。
1. ロール設定
あなたは業務分析のプロです。
2. 指示内容
以下の「具体的な業務内容」を行うために、明記されていないが必要となる「隠れたスキル(ソフトスキル含む)」を5つ挙げてください。
なぜそのスキルが必要かも解説してください。
3. 入力内容の例
・業務内容:複数のクライアントとの納期調整、エンジニアへの要件伝達、トラブル時の一次対応。No.4 チーム構成からの不足人材特定
- 目的: 既存メンバーのバランスから“次に必要な人材像”を見極める。
1. ロール設定
あなたは組織開発のスペシャリストです。
2. 指示内容
以下の「現在のチームメンバーの特徴」を踏まえ、チームのバランスを最適化するために、次に採用すべき人物のタイプ(性格や役割)を提案してください。
3. 入力内容の例
・Aさん:慎重で正確。リーダー気質。
・Bさん:アイデア豊富だが細かい作業が苦手。
・Cさん:新卒で素直だが経験不足。No.5 自社魅力の再定義(アトラクト)
- 目的: 候補者に刺さる“自社の魅力”を再整理し、アトラクト力を強化する。
1. ロール設定
あなたは採用広報のコピーライターです。
2. 指示内容
このポジションで得られる「キャリアメリット」と「やりがい」を、候補者視点で3つずつ魅力的に言語化してください。
競合他社との差別化ポイントも意識してください。
3. 入力内容の例
・ポジション:社内SE
・特徴:裁量が大きい、リモート可、古いシステムの刷新。1-2. スキルと経験を深掘りする質問

履歴書だけでは見えない“本当の実力”を見抜くためのプロンプトです。
No.6 職務経歴書からの深掘り質問生成
- 目的: 実績が本人の力によるものか、環境要因なのかを見分ける。
1. ロール設定
あなたはベテランの面接官です。
2. 指示内容
以下の「職務経歴書の要約」を読み、その実績が本人の実力によるものか、単なる環境要因かを切り分けるための「鋭い質問」を5つ作成してください。
3. 入力内容の例
・経歴概要:前職で営業売上昨対比120%を達成。チームリーダーとして5名をマネジメント。No.7 STARメソッドに基づいた行動面接
- 目的: 過去の具体的行動を引き出し、再現性をチェックする。
1. ロール設定
あなたはコンピテンシー面接の専門家です。
2. 指示内容
以下の「確認したい能力」について、STARメソッド(状況、課題、行動、結果)を用いて候補者の過去の行動を聞き出すための質問フローを作成してください。
3. 入力内容の例
・確認したい能力:困難な状況での問題解決能力No.8 失敗経験からの学習能力確認
- 目的: 失敗をどう受け止め、そこからどう成長したかを見極める。
1. ロール設定
あなたは人材育成のコーチです。
2. 指示内容
候補者が「過去の失敗」から何を学び、どう改善したかを確認するための質問リストを作成してください。
心理的安全性を確保し、本音を話しやすくする前置きの言葉も添えてください。
3. 入力内容の例
・対象:中途採用のエンジニア候補No.9 専門スキルの実践的チェック
- 目的: 単なる知識にとどまらず、応用力があるかを確かめる。
1. ロール設定
あなたは現場のプロジェクトマネージャーです。
2. 指示内容
以下の「特定のスキル」を持っているか確認するため、Yes/Noで答えられない「実践的なシチュエーション質問」を3つ考えてください。
3. 入力内容の例
・スキル:Webマーケティング(特にSEO対策)
・レベル:実務経験3年以上No.10 論理的思考力のテスト
- 目的: 答えが決まっていない問いへの“思考プロセス”を確認する。
1. ロール設定
あなたは戦略コンサルタントです。
2. 指示内容
候補者の論理的思考力と地頭の良さを測るためのフェルミ推定、またはケース面接の問題を1つ作成してください。
また、評価すべき回答のポイントも併記してください。
3. 入力内容の例
・業界:小売業界の店長候補
・難易度:中級1-3. カルチャーフィットと価値観の確認

早期離職を防ぐには、スキルだけでなく“価値観の相性”を見ることも欠かせません。
No.11 企業理念との親和性チェック
- 目的: 自社のバリューに共感しているかを確かめる。
1. ロール設定
あなたは企業のカルチャー担当役員です。
2. 指示内容
以下の「当社の企業理念(バリュー)」と照らし合わせ、候補者の価値観がそれに合致するかを確かめるための質問を3つ作成してください。
3. 入力内容の例
・企業理念:常に挑戦者であれ。スピードは質に勝る。No.12 ストレス耐性とコーピング
- 目的: ストレス環境下での対処行動を理解し、適性を判断する。
1. ロール設定
あなたは産業カウンセラーです。
2. 指示内容
業務上発生しうる「具体的なストレス状況」を提示し、候補者がどう対処するかを聞く質問を作成してください。
また、回答から読み取るべき性格特性のヒントも教えてください。
3. 入力内容の例
・状況:理不尽な顧客からのクレーム対応が続いた時No.13 チームワークと対人関係
- 目的: 協働力があり、他責思考に陥らないかを確認する。
1. ロール設定
あなたはチームビルディングのファシリテーターです。
2. 指示内容
過去のチーム内での対立や意見の不一致をどう乗り越えたかを聞き出す質問を作成してください。
「自分と合わない人とどう接するか」が見える内容にしてください。
3. 入力内容の例
・対象:協調性が求められる事務職No.14 キャリア観と自社の方向性の一致
- 目的: 候補者の未来像が、自社で実現できるのかを見極める。
1. ロール設定
あなたはキャリアアドバイザーです。
2. 指示内容
候補者の「3年後のキャリアビジョン」を聞き出し、それが当社の成長フェーズとマッチしているかを確認するための対話シナリオを作成してください。
3. 入力内容の例
・当社の状況:今はカオスだが、将来的に組織化を目指しているスタートアップ。No.15 リモートワーク適性(自律性)
- 目的: 見えない環境下でも成果を出せるかを把握する。
1. ロール設定
あなたはリモート組織のマネージャーです。
2. 指示内容
リモートワーク環境下において、どのように自己管理を行い、チームとの信頼関係を構築するかを確認するための質問を3つ挙げてください。
3. 入力内容の例
・環境:フルリモート、裁量労働制1-4. ポテンシャルと意欲を見抜く

未来の活躍を見極めるためには、少し“変化球”の質問を用意しておくのも有効です。
No.16 業界トレンドへの感度確認
- 目的: 情報収集力や学習意欲がどれほどかを測る。
1. ロール設定
あなたは業界アナリストです。
2. 指示内容
この業界の最新トレンドについて、候補者がどの程度キャッチアップし、自分の意見を持っているかを確認するディスカッションテーマを1つ設定してください。
3. 入力内容の例
・業界:SaaS業界
・テーマ:生成AIの活用についてNo.17 未経験業務への適応力
- 目的: 知らない課題に直面した時、どのような思考で動くかを確認する。
1. ロール設定
あなたは新規事業責任者です。
2. 指示内容
「全く経験のないタスク」を急に任されたと仮定し、着手から完了までのプロセスをどう設計するかを聞くシミュレーション質問を作成してください。
3. 入力内容の例
・タスク:来週までに海外競合の調査レポートを作成する。No.18 入社後のオンボーディング想定
- 目的: 入社後の立ち上がりイメージを自ら描けているかを確認する。
1. ロール設定
あなたは採用担当マネージャーです。
2. 指示内容
「もし来月入社するとしたら、最初の1週間で何をするか」を具体的に問い、候補者の能動性と準備状況を確認する質問を作ってください。
3. 入力内容の例
・ポジション:営業マネージャーNo.19 逆質問の品質評価シミュレーション
- 目的: 候補者がどの程度“本気”で会社を理解しようとしているかを推し量る。
1. ロール設定
あなたは面接官トレーニングの講師です。
2. 指示内容
優秀な候補者ならしてくるであろう「鋭い逆質問」を5つ予想してください。
また、それに対してどう答えるのがベストかもアドバイスしてください。
3. 入力内容の例
・会社の特徴:創業50年の老舗メーカーだが、若返りを図っている。No.20 アイスブレイクと本音の引き出し
- 目的: 緊張を緩め、候補者の“素の表情”や興味関心を自然に知る。
1. ロール設定
あなたはコミュニケーションの達人です。
2. 指示内容
面接冒頭で候補者の緊張を解き、かつその人の「人となり」や「熱中していること」が自然と分かるような、ユニークなアイスブレイクの質問を3つ提案してください。
3. 入力内容の例
・雰囲気:カジュアル面談2. 複数プロンプトの複合利用の方法

プロンプトは単体で使うより、組み合わせることで効果が一気に高まります。
ここでは、AIとの対話を深めながら、より精度の高い面接設計を実現するための“複合利用”のコツを紹介します。
2-1. 複合利用の基本原則
前の出力を次の入力として活用する
AIチャットの強みは、なんといっても「文脈を保持できる」点です。
たとえば、最初のプロンプトで作成した“ペルソナ”を、次のプロンプトで“質問作成の材料”としてそのまま渡すことで、一貫性のあるアウトプットが得られます。
毎回ゼロから説明する必要がないため、作業スピードも精度もぐっと上がります。
体系的なフローの構築方法
プロセスを「抽象 → 具体」の流れで組み立てると、全体がとてもクリアになります。
- まずは 要件定義
- 次に 評価基準の整理
- そこから 質問リストの作成
- 最後に 回答の評価シート化
この順番でプロンプトを紐づけることで、論理の一貫した面接設計が自然と完成します。
2-2. 初心者向けの複合利用の具体例
ここでは、実務でそのまま使える“3つの連鎖パターン”を紹介します。
例1: 募集要項から面接質問リストを一気通貫で作成
活用プロンプト:No.2(評価基準作成) → No.6(深掘り質問生成)
- No.2を実行:
募集要項を入力し、5つの評価基準を生成。 - 出力を一部選択:
その「5つの評価基準」をコピー。 - No.6を実行:
「以下の評価基準を確認するための質問を作ってください」と伝え、基準を入力して実行。
募集要項と直結した“根拠ある質問リスト”が完成します。
例2: 候補者のレジュメを読み込み、個別最適化した面接を行う
活用プロンプト:No.1(人物像の言語化) → No.8(失敗経験の確認)
- No.1を実行:
候補者の職務経歴書(個人情報は伏せる)を入力し、強み・弱みを分析。 - 出力を一部選択:
特に気になる「懸念点」や「弱み」に注目。 - No.8を実行:
「この懸念点(例:マネジメント経験不足)を確かめる質問をつくって」と依頼。
その候補者だけに最適化された“弱点を見抜く質問集”が揃います。
例3: 面接後の評価入力を効率化し、フィードバックを統一する
活用プロンプト:No.7(STARメソッド) → オリジナル(評価レポート作成)
- No.7を実行:
面接で使う質問リストを作る。 - 出力の一部を選択:
面接中のメモ(箇条書きで十分)を用意。 - オリジナルを実行:
「以下の回答を、No.7の評価軸でS〜Dにランク付けし、合否コメントをまとめて」と依頼。
感情に左右されない、統一基準の評価コメントがスピーディーに完成します。
まとめ
AIを面接に活用することは、単なる“効率化”ではありません。
人間特有のバイアスを減らし、候補者の本質にまっすぐ向き合うための強力なプロセスでもあります。
- 要件定義で「誰を採るか」を迷わない。
- 構造化された質問で「スキル」を確実に見極める。
- 複合利用によって「評価の質」を一定に保つ。
まずは、もっとも取り組みやすい 「No.1 求める人物像の言語化」 から試してみてください。
AIという鏡を通してみることで、自社が本当に必要としている人物像が、きっと鮮明に浮かび上がってくるはずです。