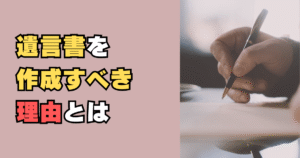はじめに
遺言は自分にはまだ早い、そう考える人は少なくありません。
ところが、突然の病気や事故は誰にでも起こり得る現実です。
もしも何の準備もなく人生の最期を迎えた場合、家族は相続をめぐって思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
仲の良かった兄弟姉妹が遺産を理由に口をきかなくなったり、配偶者が生活の基盤を失ったりするケースも少なくないのです。
遺言書は、こうした争いを未然に防ぎ、大切な人の未来を守るための重要な手段です。
しかし、いざ作ろうとすると「公正証書遺言」と「自筆遺言」のどちらを選ぶべきか迷う人が多くいます。
両者には大きな違いがあり、その選択によって将来の安心感も変わります。
この記事では、公正証書遺言と自筆遺言の特徴、費用や注意点、そして近年の法改正による新しいルールまでを整理し、実際にどちらを選ぶべきかの判断基準を解説します。
さらに、実際の事例を交えながら、あなたの人生にとって最も安心できる遺言の形を考えていきます。
終活は、誰にとっても避けられない人生の課題です。
少しでも早く取り組むことで、家族の不安を取り除き、安心して日々を過ごすことができます。
本記事を通じて、自分に最適な遺言の形を見つけていただければ幸いです。
1. 公正証書遺言の利点と費用
公正証書遺言とは、公証人が関与し、公証役場で作成される遺言書です。
公的な機関が関わるため、法的な効力が強く、最も信頼性の高い遺言の形といえます。
ここでは、公正証書遺言の具体的な利点と作成に必要な費用について見ていきます。
1-1 公正証書遺言の大きな利点
公正証書遺言には、自筆遺言にはない数々の強みがあります。
- 無効になりにくい
- 遺言は形式や内容に不備があると無効となることがあります。
- しかし、公正証書遺言は公証人が法律に則って作成するため、形式不備による無効のリスクが極めて低いのが特徴です。
- 紛失や改ざんの心配がない
- 原本は公証役場に保管されるため、本人や家族が誤って紛失することはありません。
- また、改ざんや偽造の危険も防げるため、遺言の信頼性が非常に高いといえます。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 自筆遺言では開封前に家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要がありますが、公正証書遺言はそのまま相続手続きに使用できます。
- 遺族が速やかに相続を進められる点は、大きな安心材料です。
1-2 作成に必要な手続き
公正証書遺言を作成するには、公証役場に出向き、公証人の面前で意思を確認しながら作成します。
このときには証人2名の立ち会いが必要で、証人には弁護士や司法書士などに依頼することが多いです。
【作成の流れ】
- 遺言内容の相談と原案の作成
- 公証役場にて必要書類を提出
- 公証人が内容を確認し、口述による意思確認
- 遺言書の作成・署名・押印
- 公証役場に原本保管、本人へ正本・謄本交付
この手順を踏むことで、将来的に遺言の有効性を巡って争いになる可能性は大幅に減少します。
1-3 公正証書遺言の費用
気になるのが作成費用です。費用は遺産の総額や記載内容に応じて変わります。
【公正証書遺言の費用目安】
| 遺産額 | 公証人手数料(概算) |
|---|---|
| 1000万円まで | 約2万3,000円 |
| 3000万円まで | 約2万9,000円 |
| 5000万円まで | 約3万7,000円 |
| 1億円まで | 約5万3,000円 |
| 1億円超 | 遺産額に応じて加算 |
さらに証人の日当、書類取得費用、専門家に依頼する場合の報酬がかかります。
総額としては5万円から10万円程度を見込んでおくと安心です。
1-4 公正証書遺言を選ぶべき人
- 遺産の額が比較的大きい人
- 相続人の関係が複雑な人(再婚、前妻・後妻の子がいるなど)
- 相続をめぐる争いを確実に避けたい人
- 自筆で書く自信がない、または健康状態が不安な人
こうした条件に当てはまる場合、公正証書遺言は最も安心できる選択肢となります。
多少費用はかかりますが、それ以上の安心感と家族への配慮を得られる点で非常に価値があります。
2. 自筆遺言のメリットと注意点
自筆遺言とは、その名のとおり本人が自らの手で書き残す遺言書のことです。
もっとも古くから利用されている方式であり、思い立ったときにすぐに作成できる点が特徴です。
しかし、その気軽さの一方で、多くの落とし穴も存在します。
ここでは、自筆遺言の具体的な利点と注意すべき点を整理していきます。
2-1 自筆遺言のメリット
まずは、自筆遺言が持つ大きな利点を確認しましょう。
- 費用がかからない
- 公証役場に支払う手数料も不要で、紙とペンがあれば誰でも作成できます。
- 最もコストが低い遺言方式です。
- 思い立ったときにすぐ作れる
- 専門家や証人の立ち会いは不要です。
- 家にいながら短時間で作れるため、健康状態が変わったときや急いで意思を残したいときに有効です。
- 内容を秘密にできる
- 公正証書遺言は証人の立ち会いが必要ですが、自筆遺言は誰にも見せずに書き残せます。
- 家族に知られたくない特別な想いを残したい場合には適しています。
2-2 自筆遺言の大きな注意点
しかし、自筆遺言には危険が潜んでいます。
- 形式不備で無効になるリスク
- 遺言書には「全文自筆」「日付」「署名」「押印」などの要件があります。
- 一つでも欠けると無効になりかねません。
- 紛失・破棄される可能性
- 自宅に保管する場合、家族が知らずに処分してしまったり、意図的に隠してしまうリスクがあります。
- 家庭裁判所での検認が必要
- 自筆遺言は相続開始後、家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければ効力を発揮できません。
- この手続きに数週間から数か月かかることがあり、遺族の負担になります。
2-3 法改正により広がった選択肢
2019年の民法改正により、自筆遺言の利便性は以前より高まりました。
特に以下の点が変更されています。
- 財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が可能
- 法務局での遺言書保管制度が開始(2020年7月~)
これにより、自筆遺言であっても紛失の心配を減らし、検認手続きが不要となるケースが生まれました。
2-4 自筆遺言を選ぶべき人
- 遺産の額が少なく、分け方が単純な人
- 費用をかけずに意思を残したい人
- 急いで遺言を作成する必要がある人
- 自分の気持ちを整理するためにまず書いてみたい人
ただし、これらに当てはまっても、後に修正や補強をしないまま放置すると無効のリスクが残ります。
自筆遺言は「第一歩」としての意味が強く、最終的には公正証書遺言で確定させる人も少なくありません。
3. 法改正で変わった作成要件
遺言制度は、時代に合わせて見直されてきました。
近年の民法改正により、遺言書の作成や保管に関するルールが大きく変わっています。
この変化を理解していないと、「せっかく遺言を書いたのに効力がない」という事態を招きかねません。
ここでは、近年の改正ポイントを整理し、遺言を確実に残すための注意点を解説します。
3-1 財産目録の自筆義務が緩和
以前は遺言書に記載するすべての内容を自筆で書かなければなりませんでした。
たとえば、不動産の登記簿謄本の内容や銀行口座番号も手書きする必要があり、誤記や記載漏れが頻発していました。
しかし、2019年の法改正により、財産目録については自筆でなくてもよいとされました。
- パソコンで作成した一覧表の添付が可能
- 通帳や登記事項証明書のコピーをそのまま添付できる
- ただし、各ページに署名・押印は必要
この改正により、長文を自筆する負担が軽減され、正確性も高まっています。
3-2 法務局での遺言書保管制度
2020年7月からは「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
これは、自筆遺言を法務局に預けられる仕組みです。
【特徴】
- 法務局が遺言書を原本のまま保管
- 相続開始後は、相続人が全国の法務局で閲覧・写しを取得可能
- 家庭裁判所の検認が不要(保管制度を利用した場合のみ)
従来は「自筆遺言=紛失リスク・検認手続きが必要」というイメージでしたが、この制度により信頼性が格段に向上しました。
3-3 デジタル化への期待と課題
今後はデジタル化の流れも進むと考えられますが、現時点ではパソコンで全文作成した遺言は無効です。
自筆遺言であれば、必ず全文を自筆する必要があります。
つまり、利便性は高まったものの「紙に自分で書く」基本ルールは変わっていません。
また、遺言の保管制度を利用するには本人が法務局に出向く必要があり、代理申請はできません。
高齢者や病気で外出が難しい人にはまだハードルが残っているのも事実です。
3-4 法改正がもたらしたメリットと安心感
これらの改正により、以前よりも次のような安心が得られるようになりました。
- 記載ミスや負担が減った
- 紛失・隠匿のリスクを大幅に減らせる
- 相続手続きがスムーズに進められる
一方で、改正内容を正しく理解しないまま古い形式で遺言を残してしまうと、せっかくの意思が反映されない恐れもあります。
制度の変化を知り、最新のルールで作成することが大切です。
4. どちらを選ぶべきかの判断基準
公正証書遺言と自筆遺言は、それぞれに利点と注意点があります。
大切なのは「自分の状況に合った方式を選ぶこと」です。
ここでは、判断基準をいくつかの視点から整理してみます。
4-1 費用を優先するか、安心を優先するか
- 費用をかけたくない場合
- 自筆遺言が有力です。
- 紙とペンさえあれば作成でき、初期費用はほとんど不要です。
- 特に財産が少額で、相続人も少なく単純な分け方で済む場合に向いています。
- 将来の安心を優先したい場合
- 公正証書遺言が適しています。
- 費用は数万円かかりますが、形式不備の心配がなく、相続人が速やかに手続きを進められる点で安心感があります。
4-2 家族関係が円満か、それとも複雑か
- 家族関係が円満で、争いが起こりにくい場合
- 自筆遺言でも十分に機能する可能性があります。
- 例えば、子どもが一人だけの場合や、配偶者だけが相続人の場合などです。
- 家族関係が複雑、または争いの火種がある場合
- 公正証書遺言が必須に近い選択です。
- 再婚で子どもが複数の家庭にまたがっている場合、兄弟姉妹の仲が悪い場合、事業を承継する場合などは、法的に確実な遺言でなければトラブルを防ぎきれません。
4-3 健康状態や年齢からみる選択
- 若くて元気なうちに気軽に始めたい人
- 自筆遺言で第一歩を踏み出すのが良いでしょう。
- まずは書くことで自分の財産や想いを整理できます。
- 高齢、または病気で意思能力に不安がある人
- 公正証書遺言を選ぶべきです。
- 公証人が本人の意思を確認するため、後に「本当に本人の意思だったのか」と疑われる可能性を大幅に減らせます。
4-4 専門家のサポートを受けるかどうか
- 自分で完結したい場合
- 自筆遺言は自由度が高く、思い立ったらすぐに書けます。
- ただし、その分リスクもあるため、定期的に見直すことが大切です。
- 専門家の助けを借りたい場合
- 公正証書遺言を選び、弁護士や司法書士に相談すると、より確実性の高い内容を作れます。
- 特に財産分けに悩む場合には有効です。
4-5 判断基準を表に整理
わかりやすく比較すると以下のようになります。
| 観点 | 公正証書遺言 | 自筆遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | 数万円必要 | ほぼ不要 |
| 安心感 | 高い(無効化リスク低い) | 低い(不備で無効の恐れ) |
| 手続き | 証人2人・公証人の関与 | 本人のみで作成可能 |
| 保管 | 公証役場で保管 | 自宅 or 法務局保管制度 |
| 家族関係 | 複雑でも安心 | 単純な場合向き |
| 健康状態 | 高齢・病弱に安心 | 若く元気なうちに有効 |
どちらか一方だけが絶対に正しい選択肢ではありません。
大切なのは、自分や家族の状況を冷静に見つめ、将来の安心をどう優先するかを考えることです。
5. 実際の事例で見る使い分け
理屈では理解できても、実際にどのような場面で公正証書遺言や自筆遺言が使い分けられるのかは、具体例を見ることで初めてイメージできます。
ここでは、よくあるケースを3つ取り上げ、遺言方式の選択が家族にどのような影響を与えるかを解説します。
5-1 事例1:子どもが一人の家庭
Aさん(65歳)は妻と一人息子の3人暮らし。
財産は自宅と預金のみです。
このような場合、相続人は配偶者と子どもだけであり、争いになる可能性は比較的低いと考えられます。
Aさんは最初に自筆遺言を作成しました。
費用もかからず、思い立ったときに書けるため、スムーズに準備が進みました。
ただし、後に法務局の保管制度を利用して正式に預けたことで、紛失の心配がなくなり、家族も安心できました。
→ 財産が少なく相続人がシンプルな家庭では、自筆遺言+法務局保管が有効 という好例です。
5-2 事例2:再婚で子どもが複数いる家庭
Bさん(72歳)は再婚しており、前妻との間に子どもが2人、現在の妻との間に子どもが1人います。
財産は不動産や株式など多岐にわたり、相続人同士の関係は複雑です。
このケースでは自筆遺言では危険が伴います。
もし記載に不備があれば無効となり、遺産分割協議で争いが避けられません。
Bさんは弁護士に相談し、公正証書遺言を作成しました。
公証人が内容を確認し、証人立会いのもとで作成したため、相続開始後もスムーズに手続きが進みました。
→ 家族関係が複雑な場合は公正証書遺言が不可欠 です。
5-3 事例3:事業承継を考える経営者
Cさん(68歳)は小さな会社を経営しており、長男に事業を継がせたいと考えています。
会社の株式や事業資産をどう分けるかは、遺産分割の中でも特に争いになりやすいテーマです。
この場合、単に「会社を長男に相続させる」と自筆で書くだけでは不十分です。
株式の割合や他の相続人への配慮を明確にしておかないと、後に訴訟に発展する可能性があります。
Cさんは税理士・司法書士と連携し、公正証書遺言に加えて「遺言執行者」の指定まで行いました。
→ 事業や不動産が絡む場合は、専門家と共に公正証書遺言を作ることが最も安心 といえます。
5-4 事例から学べること
- 自筆遺言は第一歩として有効。ただし放置せず、法務局保管や定期的な見直しが必要。
- 公正証書遺言は費用がかかるが、複雑な相続や争いを避けたい場合には必須。
- 専門家の関与があるかどうかが安心の分かれ道。
遺言の形式を選ぶことは、未来の家族関係を守る選択に直結します。
事例を参考にしながら、自分の状況に重ねて考えることが大切です。
まとめ
遺言は「まだ先のこと」と思われがちですが、突然の病気や事故は誰にでも起こり得ます。
準備を怠れば、残された家族が相続をめぐって争いに巻き込まれる危険があります。
今回の記事では、公正証書遺言と自筆遺言の違いを整理しました。
- 公正証書遺言は費用がかかるものの、無効の心配がなく、最も確実で安心できる遺言です。
- 自筆遺言は手軽で費用もかからず、「まず一歩」を踏み出すには最適ですが、形式不備や紛失のリスクが残ります。
- 法改正により、自筆遺言でも財産目録の簡便化や法務局での保管制度が利用できるようになり、信頼性が高まりました。
- 実際の事例を見ると、相続が単純な場合は自筆遺言、家族関係や財産が複雑な場合は公正証書遺言が有効であることが分かります。
最終的にどちらを選ぶかは、財産の規模や家族の状況、そして安心をどれだけ重視するかで決まります。
大切なのは「どちらを選ぶか」で悩み続けることではなく、今すぐに一歩を踏み出すことです。
その一歩が、家族を守り、自分自身も安心して暮らすための礎となります。