はじめに
読書感想文を書く――それは、毎年多くの子どもと保護者にとって頭を悩ませる宿題の一つです。
「何を書けばいいのか分からない」「気づけば時間だけが過ぎている」――そんな声をよく耳にします。
特に、本の要点を整理したり、自分の考えを言葉にする作業は、慣れていなければとても大変に感じるものです。
そこで注目したいのが、AIを“要約と論点整理のアシスタント”として活用するという発想です。
AIにあらすじをまとめてもらい、論点を整理してもらうだけで、「書き始め」のハードルが一気に下がります。
この記事では、親子で一緒に取り組める具体的なステップと、すぐに使える実践プロンプトを紹介します。
読書感想文を“代筆”にするのではなく、子どもの思考を引き出す道具としてAIを活用する方法を、やさしく解説していきます。
1. 読書感想文の負担を軽減
読書感想文ほど、「どう書けばいいか分からない」宿題はありません。
親も子も、いざ取りかかろうとしても手が止まる──そんな光景は、夏休みの定番とも言えます。
でも、本当の原因は「書く力」ではなく、“整理する力”が足りないだけなのかもしれません。
ここでは、AIを使って「情報整理」と「書き出しのハードル」を一気に軽くする方法を紹介します。
親子で“迷いのないスタート”を切るコツを見ていきましょう。

1-1. なぜ負担が大きいのか
① 情報の整理が苦手
本の中には、さまざまなエピソードや登場人物、背景やテーマが詰め込まれています。
その中からどれを選び、どうまとめるかを考えるのは、子どもにとって至難の業です。
特に、最初の一段落で「何を書くか」が決まらないと、その後の筆も進みません。
② 自分の意見が出てこない
「感想を書こう」と言われても、どんな視点で評価すればいいのか分からない。
比較対象――たとえば別の本や自分の体験――がなければ、どうしても抽象的な言葉に終わりがちです。
③ 時間とモチベーションの不足
期限が決まっている宿題では、「早く書かなくちゃ」と焦るあまり内容が浅くなってしまうことも。
計画的に進める仕組みや、途中でフィードバックを得られる環境がないと、完成度も上がりにくいのです。
AIを取り入れることで、一瞬で「要点の骨組み」が提示されるようになります。
これにより、子どもは「何を書けばいいか」で詰まることが減り、感想文にかかる時間も大幅に短縮。
保護者は、子どもの思考を深める質問や対話に集中でき、親子の共同作業としてもスムーズに進められます。
1-2. 実践手順:親子で進める3ステップ
① まずは本の基本情報を入力する
本のタイトル、著者、ページ数、読んだ範囲(章など)をAIに伝えましょう。
たったこれだけで、AIは文脈を理解し、前提を押さえた上で回答を準備してくれます。
② AIにあらすじを作らせる(短め→詳細へ)
最初は「100字であらすじをまとめて」と頼み、次に「登場人物の関係や大事な出来事を400字で」と指示します。
短い要約から段階的に深めていくことで、内容理解が自然に定着していきます。
③ 親が子どもの口から“一文”を引き出す
AIが出した要約を見せながら、「どの場面が一番印象に残った?」と問いかけてみましょう。
子どもが答えた一文をAIに渡して骨子を作らせれば、自然と感想文の形が見えてきます。
実用プロンプト(初期用)
本情報:
タイトル:「○○」
著者:○○
読んだ範囲:1章〜3章
指示:
1) 100字で本のあらすじを作ってください。
2) 登場人物と関係を200字で説明してください。
3) 子どもが使いやすい質問(5つ)を作ってください(簡潔な日本語で)。
出力形式:1,2,3を見出し付きで。この流れ――あらすじ→質問→子どもの一文→AIの整文という循環が生まれると、子どもの表現力は短期間で大きく伸びます。
初めての感想文でも「書き出しのつかみ」が安定し、完成までスムーズに進む。
書き終えたときの達成感も格別です。
2. 本のテーマを深掘りする
感想文が薄く感じられるのは、「何について書きたいのか」がぼやけているから。
AIを活用すれば、物語に隠れたテーマや作者のメッセージを浮き彫りにできます。
ここでの目的は、ただ要約を作ることではありません。
AIを“考える鏡”として使いながら、子ども自身の感情と物語のテーマをつなげていくことです。
その具体的なステップを、一緒に見ていきましょう。
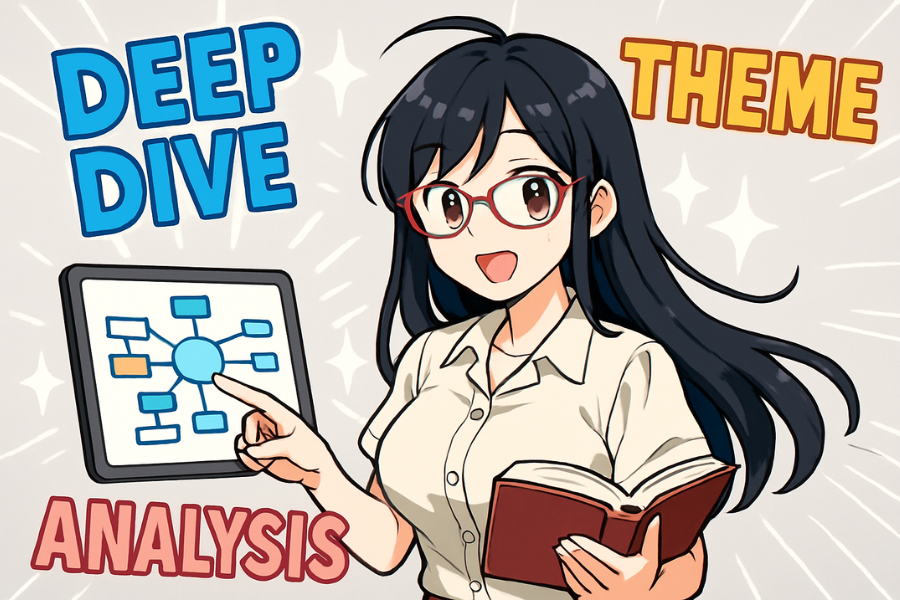
2-1. テーマ抽出のやり方
① キーワード抽出
まず、AIに本の要約を渡し、よく使われている言葉や重要なキーワードを抜き出してもらいます。
そこから「友情」「勇気」「成長」といったテーマ候補を3つ提示してもらうのがポイントです。
一見単純な作業に思えるかもしれませんが、これをAIに任せるだけで「この本は何を伝えたかったのか」が一気に見えてきます。
② 場面とテーマの紐付け
次に、物語の中で印象的な場面を3つ挙げ、それぞれがどのテーマを表しているのかを説明させます。
たとえば「友達をかばうシーン=友情」「失敗しても挑戦を続ける=成長」といった具合に、場面とテーマをつなげると、感想文全体の流れが自然に整理されていきます。
この段階で「何を中心に書くか」がはっきりしてくるでしょう。
③ 作者のメッセージを推測する
最後に、登場人物の選択や物語の結末から、作者が伝えたかったメッセージを短文でまとめます。
これはそのまま感想文の結論部分に使える材料になります。
「この物語は“勇気を出して一歩踏み出すこと”の大切さを伝えている」など、AIが導き出す一文が、文章の締めに深みを与えてくれます。
実用プロンプト(テーマ抽出)
前提:以下は本の要約です(貼付)。
指示:
1) 重要キーワードを上位10個抽出してください。
2) キーワードを基に考えられるテーマを3つ提示してください(各テーマを40〜60字で説明)。
3) 物語の重要場面3つを挙げ、それぞれが示すテーマを一行で説明してください。
出力形式:箇条書き+簡潔な説明2-2. 親子で進める「深掘りセッション」
① 読んだ場面を選ぶ
まず、子どもに「一番好きな場面」や「印象に残った場面」を選んでもらいましょう。
もし迷ってしまうようなら、AIに提案してもらった重要場面の中から選ばせても構いません。
「どれが一番心に残った?」という質問だけでも、思考が動き始めます。
② 感情と理由を言葉にする
次に、「その場面でどんな気持ちになった?」「なぜそう思った?」と聞いてみてください。
子どもの答えをまず受け止め、そのうえでAIに整理してもらうと、ぼんやりした感情が自然な文章として形になります。
AIが補助輪のように感情を整えてくれるのです。
③ テーマと結びつける
ここで、さきほど抽出したテーマ(友情・勇気・成長など)と、子どもの感情をつなぎ合わせます。
AIに「この感情はどのテーマに近い?」と尋ねると、「友達を信じる気持ちは“友情”のテーマに当てはまります」といった具合に整理してくれます。
この作業によって、感想文の「結論部分」が驚くほどスムーズに書けるようになります。
このプロセスを通じて、子どもは単なる“あらすじの要約”ではなく、物語の意味や作者の意図を、自分の言葉で語る力を身につけていきます。
親もサポートしやすく、無理なく“自分で考える読書”へと導けるのが、この方法の最大の魅力です。
3. 自分の意見を明確化
「感じたことはあるけど、うまく言葉にならない」──多くの子どもが抱える悩みです。
実は、感想文に必要なのは「語彙力」よりも“構造的な考え方”。
AIは、その思考の道筋をやさしく整えてくれます。
感情と理由を分け、意見を整理し、自分の言葉で語る。
ここでは、AIを“論理の補助線”として使うことで、感想文の質をぐっと高める方法を紹介します。

3-1. 「感想」を構造化して考える
多くの子どもが読書感想文でつまずくのは、「感じたことをどう書けばいいか分からない」という点にあります。
でも、感想文は実は立派な“意見文”。
つまり、感情にも“根拠”と“背景”が必要なんです。
AIをうまく使えば、この構造を自然に身につけることができます。
① 感情と理由を分ける
AIに「この本を読んで感じたことを3つ挙げて」と伝えると、「感動した」「悲しかった」「おもしろかった」など、感情のリストが出てきます。
そこでさらに「なぜそう感じたの?」とAIに尋ねると、「主人公が諦めずに努力していたから」「家族の絆を感じたから」など、感情に対応する具体的な根拠をセットで提示してくれます。
これを繰り返すことで、自然と「理由のある意見」が作れるようになります。
② 対比構造で考える
意見を深めるもう一つの方法が、「もし自分だったら?」という視点を加えること。
AIに「主人公と反対の立場で考えると?」と聞くと、「もし自分なら逃げたかもしれない」「別の選択をしたかもしれない」といった対立する視点が返ってきます。
この対比があるだけで、文章に厚みと説得力が生まれます。
③ 意見を一文にまとめる練習
AIが出してくれた案を参考にしながら、「一番伝えたい考え」を短く明確な一文にまとめてみましょう。
主語と述語を意識して書くと、感想文の“軸”がしっかり定まります。
実用プロンプト(意見整理用)
前提:以下は子どもの感想のメモです(貼付)。
指示:
1) 感情と理由を分けて表に整理してください。
2) 「自分だったらどうするか」という視点で、反対の考えを3つ挙げてください。
3) 最後に「自分の意見」を一文にまとめるための文例を3つ作ってください。
出力形式:表+リスト+文例この手順で整理を進めると、AIが感情と根拠を自動で分離してくれます。
結果、子どもの思考は「なんとなく思った」から「理由のある意見」へと変化していきます。
論理的な考え方が身につき、国語だけでなく他の教科にも良い影響を与えるはずです。
3-2. 感情語彙を増やして表現を広げる
感想文では「すごい」「よかった」だけでは気持ちが十分に伝わりません。
ここでAIを“感情辞典”のように使うと、表現が一気に豊かになります。
① 似た感情の言葉を出してもらう
たとえば「悲しい」と入力すると、AIは「切ない」「虚しい」「苦しい」「寂しい」など、微妙に違うニュアンスの言葉をリスト化してくれます。
その中から、子どもが自分の気持ちに一番合う言葉を選べばいいのです。
これだけでも、文章に深みが出ます。
② 使い方の例を出してもらう
AIに「“切ない”を使った例文を3つ出して」と頼むと、実際の文脈を踏まえた例文を提示してくれます。
そのまま書き写すのではなく、「どんな場面で使える言葉なのか」を話しながら確認することで、自然と語彙力が身につきます。
③ 感情の強弱を表で理解する
さらに、「悲しい→怒りに近い順に並べて」と頼むと、AIが感情の強さを数値化した表を作ってくれます。
この“感情のグラデーション表”を見ながら「今の気持ちはどの辺かな?」と考えると、表現のトーンをうまく調整できるようになります。
実用プロンプト(感情語彙用)
指示:
1) 「悲しい」という感情に近い言葉を10個挙げてください。
2) それぞれの言葉を使った例文を1文ずつ作ってください。
3) 感情の強さ(1〜5)を数字で示してください。
出力形式:表(言葉/例文/強さ)この方法を使うと、「言葉が出てこない」時間が減り、「書くことが楽しい」時間が増えるようになります。
AIをうまく使いこなすことで、子どもは自然に語彙力を広げ、より生き生きとした感想文を書けるようになっていくのです。
4. 構成案の自動生成
いきなり書き始めると、途中で迷子になりがちです。
どんなに良い考えがあっても、構成の地図がないとゴールまでたどり着けません。
AIに構成づくりを手伝ってもらうと、文章の流れが自然に整い、書きやすさが驚くほど変わります。
ここでは、“書く前に考える力”を育てるAIの使い方を具体的に紹介します。
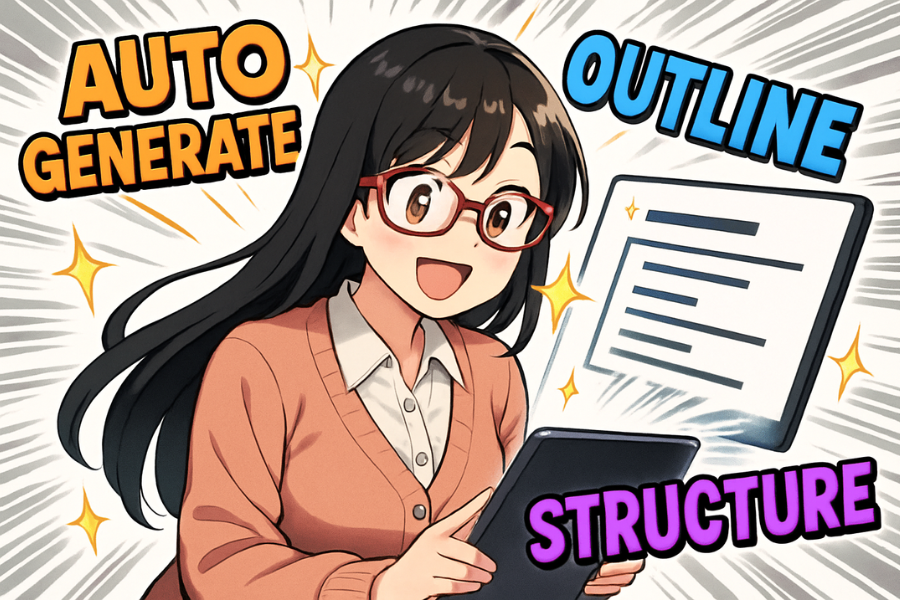
4-1. 感想文の基本構成を理解する
感想文を書くとき、「何から書き始めればいいか分からない」と悩む子は少なくありません。
でも実は、感想文には共通する“型”があります。
それをAIに学ばせ、テンプレート化しておくことで、文章の流れが一気にスムーズになります。
① 基本の4段構成を把握する
一般的な感想文は次のような順序で組み立てます。
| 段階 | 内容 | 例文 |
|---|---|---|
| 導入 | 本を選んだ理由・概要 | この本を選んだのは、表紙の絵にひかれたからです。 |
| 展開 | 印象に残った場面・人物 | 主人公があきらめず挑戦する姿に心を打たれました。 |
| 深掘り | そこから考えたこと・学び | 努力を続ける大切さをあらためて感じました。 |
| 結論 | 自分へのメッセージ・まとめ | 私も目標に向かって挑戦を続けたいです。 |
この型に沿ってAIに「構成案を作って」と指示すれば、子どもの思考を整理しながら文章を整えてくれます。
② 構成を自動生成させる
AIに「本のタイトル」と「印象に残った場面」を入力し、「感想文の構成案を400字以内で」と頼むだけで、全体の流れを示すプロットを自動で作成できます。
このとき「小学生でも理解できる表現で」と指定しておくと、より実用的な出力になります。
③ 構成を“ひな形”として保存する
作成された構成案は、次の課題や他の本でも使い回せます。
特に作文が苦手な子どもほど、“成功パターン”をAIで残しておくと、次に書くときのハードルがぐっと下がります。
実用プロンプト(構成案作成用)
本のタイトル:「○○」
印象に残った場面:「○○」
指示:
1) 小学生でも理解できる言葉で、感想文の構成案(導入・展開・深掘り・結論の4段構成)を作ってください。
2) 各段落の内容を1〜2文ずつ説明してください。
3) 文章のつながりが自然になるように提案してください。
出力形式:段落番号+内容説明AIが構成案を作ってくれると、子どもは「どの順番で書けばいいか」が明確になります。
文章の流れに迷わなくなり、親も修正やアドバイスをしやすくなります。
AIが“見えない台本”を用意してくれることで、感想文づくりが安心して進められるのです。
4-2. 書き出し・結びをAIに提案させる
文章の印象を決めるのは、冒頭と結びです。
ここをAIに手伝ってもらうと、読みやすさがぐっと上がります。
① 書き出しの提案を受ける
AIに「この内容で書き出し文を3案ください」と伝えると、
「私はこの本を読んで○○という気持ちになりました」など、自然な文を提示してくれます。
中でも自分らしい言葉を選べば、冒頭から読者を惹きつける一文になります。
② 結びの文を整える
最後の一文には、感想のまとめと“今後の自分”を入れるのがポイントです。
AIに「この内容で締めくくり文を作って」と指示すれば、「これからは○○を大切にしていきたいです」といった自然な結びが出力されます。
③ 文体を統一する
AIの提案をもとに「〜です・〜ます調」にそろえるだけで、全体のトーンが整います。
語尾を統一する作業はAIに任せても構いません。
実用プロンプト(書き出し・結び)
感想文の構成案を基に:
1) 書き出し文を3案提案してください(小学生向けの語彙で)。
2) 結びの文を3案提案してください(前向きな印象で)。
3) 文体を「です・ます」に統一してください。
出力形式:番号付きリストAIが文の“最初と最後”を整えてくれるだけで、感想文の印象は驚くほど良くなります。
「きれいにまとまった」と感じられる成功体験は、子どもの文章への苦手意識を軽くし、次のチャレンジへとつながっていきます。
5. 親子の対話を促す活用法
AIを使った感想文づくりの本当の価値は、「一緒に考える時間が増えること」にあります。
AIが会話のきっかけを作り、親はサポートに回り、子どもは自分の考えを育てていく。
その過程こそが、学びの核心です。
ここでは、AIを「代筆者」ではなく「対話のパートナー」として使う方法を、具体的なプロンプトとともに紹介します。

5-1. AIを“会話の橋渡し役”にする
AIは単なるツールではなく、親子の会話を引き出す媒介としても使えます。
親が「どう感じたの?」と聞いても、子どもがなかなか答えないことはよくあります。
そんなとき、AIに「子どもが答えやすい質問を作って」と頼むと、たとえば「もし自分が主人公ならどうした?」など、柔らかい質問を生成してくれます。
この質問をきっかけに、親子の自然な対話が生まれるのです。
➀ 会話の記録を残す
AIチャット上で親子の会話を続けると、その内容がすべて“記録”として残ります。
子どもの思考の変化や成長を後から振り返ることができ、「去年より自分の意見が増えたね」といったフィードバックにも活かせます。
➁ 褒める材料として使う
AIがまとめた内容を見ながら、「こんなに考えられているね」「ここが素敵だね」と言葉にすることで、子どもは自信を持ち、次の課題にも前向きになります。
AIが出力した文章を「そのまま提出」するのではなく、親子で確認し、磨いていくことが大切です。
5-2. 「AI=代筆」ではなく「思考の補助輪」
AI活用で誤解されがちなポイントがあります。
それは「AIに書かせる=ズル」だと思われてしまうこと。
けれど、ここで大事なのはAIを“思考の補助輪”として使うことです。
AIは考え方の順序を整え、言葉を引き出すサポーター。
自転車の補助輪のように、最初は支えながら、徐々に自分の力で走れるよう導いてくれます。
最終的に書くのは子ども自身。そのプロセスを通じて、「自分の考えを持ち、それを言葉にできる力」が育っていくのです。
まとめ
読書感想文の最大の壁は、「書き出せないこと」と「何を書けばいいか分からないこと」。
AIを上手に使えば、その壁をあっさり越えられます。
AIはあらすじを整理し、テーマを導き、構成を整え、書き出しと結びまで提案してくれる。
親子で一緒にAIを使えば、宿題という義務が“思考のトレーニング”に変わります。
最初は小さな一文からでも大丈夫。
AIに手を借りながら、「自分の言葉で伝える喜び」を少しずつ積み重ねていきましょう。





