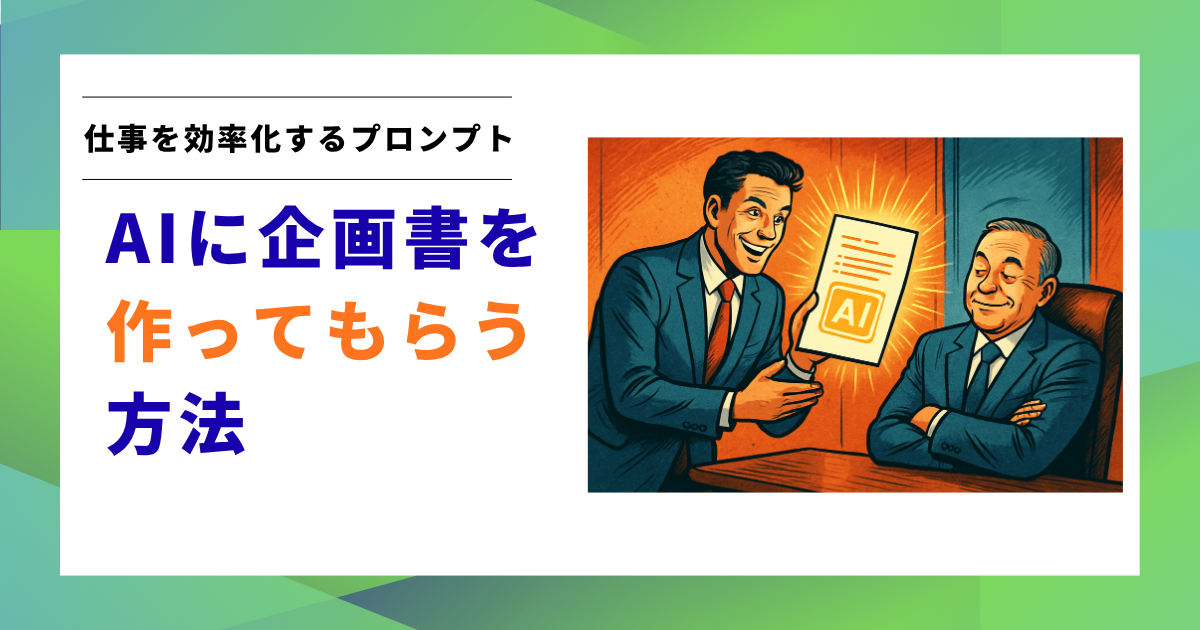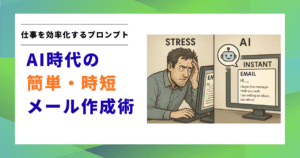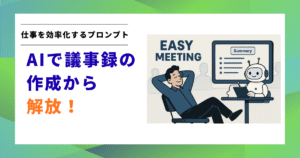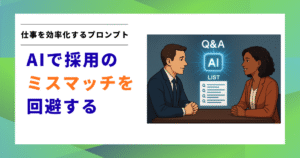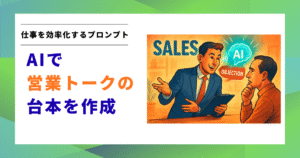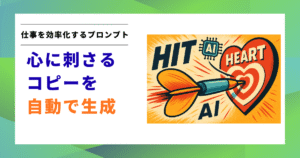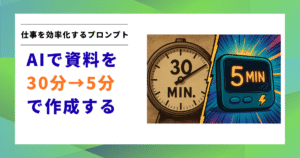はじめに
ゼロから企画書を作るのは、想像以上に時間がかかります。
構成を考え、論点を整理し、書きながら修正を重ねていくうちに、気づけば何時間も経過している。
「どこから書けばいいかわからない」「そもそも論点がまとまらない」──そう感じた経験がある人は少なくありません。
多くの人が勘違いしているのは、「企画書は最初から自分の頭で作るもの」という思い込みです。
けれど本質は違います。企画の価値は“最初の構成”で8割決まるのです。
AIを使えば、この“構成(骨子)”と“論点”を一瞬で可視化できます。
つまり、「ゼロから考える」という最も時間のかかる作業をスキップできるということです。
この記事では、AIに「骨子と論点」を自動で出させる最強プロンプトを活用し、
企画倒れを防ぎ、説得力のある企画書を最短で作るための具体的なステップを紹介します。
思考の整理・情報収集・構成作成──そのすべてをAIに任せる新しい企画術を体験してください。
1. 企画倒れを防ぐAI活用
企画がうまくいかないのは、「アイデアが悪い」からではありません。
多くの場合、構成の段階でつまずいているのです。
方向性が定まらないまま資料を作り始めると、途中で論理が破綻したり、説得力を失ったりします。
AIは、まさにその“出発点”を正しく整える最強の補助輪になります。

1-1. なぜ企画は途中で止まるのか
① 論点が整理されていない
「新しい施策を打ちたい」「顧客を増やしたい」──目的は明確でも、
“なぜ今それをやるのか”、“どう成功を測るのか”が曖昧なまま進むと、企画は迷走します。
AIに「この目的を達成するために考慮すべき論点を3つ挙げて」と聞くだけで、
人間では見落としがちな観点(コスト、実現性、リスクなど)を整理してくれます。
② 情報の偏り
手持ちの情報や経験に頼りすぎると、視野が狭くなります。
AIは大量の視点を横断的に整理し、市場・競合・顧客ニーズを網羅的に並べてくれます。
つまり、“自分の思考の外側”を一瞬で可視化できるのです。
③ 書き出しで止まる
白紙に向かって最初の一文を書くのは、想像以上にエネルギーを使います。
AIに「このテーマで企画書の構成案を5パターン出して」と指示すれば、
最初の“型”が手に入り、書く作業が圧倒的に楽になります。
1-2. AIを「構成作成」に使うと何が変わるのか
① 思考のスピードが10倍になる
AIが提示する構成案は、論理の流れがすでに整理されているため、
自分はそれを選び、修正するだけで済みます。結果、ゼロベースで考えるより圧倒的に早く進められます。
② 発想の幅が広がる
自分一人では出せない観点を、AIがどんどん提案してくれます。
「A案の視点でB市場にも展開できる」「リスク視点を先に出すと説得力が上がる」など、
構成の“発想補助”としてAIを使うと、質と量の両面で成果が上がります。
③ AIプロンプトの基本形
目的:30代女性向けに新しい定期便サービスを企画したい
条件:競合は3社、価格帯は月額2,000円〜3,000円、初回は無料
出力:企画書の構成案(5章立て)と、それぞれの章の主要論点3つこのように目的と前提を整理して渡すだけで、AIは即座に「読むだけで通る構成」を出してきます。
④ AIの出力を「比較して選ぶ」
1案に頼らず、必ず複数パターンを生成して比較するのがポイントです。
「上司が好む堅めの構成」「顧客プレゼン向けの構成」「短期施策用の構成」など、
AIに“文脈”を変えて依頼することで、最適解を見つけやすくなります。
2. 企画書の必須要素とは
どんなに良いアイデアでも、企画書としての形を欠いていれば通りません。
プレゼンに必要なのは「面白さ」ではなく、「納得させる構造」です。
AIを使えば、欠かせない要素を漏らさず整理し、読まれる企画書を短時間で整えられます。
2-1. 企画書に欠かせない5つの要素
① タイトルと要約(結論を先に伝える)
読み手が最初に見るのはタイトルです。ここでつまずくと、中身は読まれません。
AIに「この内容を一文でキャッチーにまとめて」と依頼し、複数案を比較して決めると精度が上がります。
② 背景・課題の明確化
“なぜ今この企画が必要なのか”を、データと現状の問題点で説明します。
AIに社内データや市場情報を与え、「現状の課題を3行で要約して」と指示するだけで、
客観的で伝わりやすい背景を自動で作成できます。
③ 目的・提案・効果
施策のゴールを明確に示し、提案内容と期待できる成果をセットで提示します。
「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかを具体的に。
AIには「提案と効果をKPI付きで書いて」と指示すると、数字を伴う説得力ある内容に変わります。
④ 実行スケジュールと担当体制
実現可能性を見せるためには、行動計画の明示が不可欠です。
AIに「3か月間の実施スケジュールを週単位で提示して」と依頼すれば、
現実的な実行ロードマップが即座に生成されます。
⑤ リスクと対策
承認者が最も注目するのは「リスクをどう想定しているか」です。
AIに「この企画におけるリスクを3つ挙げ、それぞれの回避策を提案して」と入力すれば、
安心感と信頼性を与える説得力ある終盤が完成します。
2-2. AIを使った構成の仕上げ方
① “全体の流れ”を先に決める
骨子が出たら、まず章立てを俯瞰して並べ替えます。
AIの出力は完璧ではないため、「読み手が理解しやすい順」に手を加えることが大切です。
② “具体化”をAIに任せる
「第3章に詳細な施策を追加して」とAIに依頼すれば、肉付けが自動で進みます。
つまり、人は構成の編集者に徹し、AIが執筆者になるのが最も効率的なスタイルです。
③ “声のトーン”を調整する
企画書は相手によって言葉遣いを変える必要があります。
AIに「上司向けにフォーマルに」「クライアント向けに柔らかく」とトーンを指定すれば、
短時間で複数バージョンを作ることができます。
3. AIによる競合分析の自動化
企画書で最も重要なパートのひとつが競合分析です。
ところが、多くの企画書ではこの部分が薄く、「参考までに競合A社の事例」といった表面的な比較で終わってしまうケースが多い。
本来、競合分析は「自社の優位性を論理的に説明するための土台」であり、ここが弱いと企画全体の説得力が一気に落ちます。
AIを使えば、膨大な競合情報を短時間で整理し、比較軸を自動で作成することができます。
この章では、AIによる競合分析の手順と、活用すべきプロンプトを具体的に紹介します。
3-1. AIが得意な「俯瞰分析」
AIは、あるテーマに対して全体構造を把握する力に優れています。
例えば次のように指示するだけで、数分で分析のたたき台が完成します。
テーマ:サブスク型コーヒーサービス
指示:主要な競合を3社挙げ、それぞれの特徴・価格帯・強み・弱みを比較表で整理してください。AIはこの指示をもとに、以下のような表を作ってくれます。
| 競合 | 価格帯 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|
| A社 | 月額2,500円 | コーヒー豆の品質が高い | 配送の柔軟性が低い |
| B社 | 月額1,980円 | 手軽に始められる | ブランド力が弱い |
| C社 | 月額3,200円 | 体験型イベントを併設 | コストが高い |
この表を眺めるだけで、市場の位置関係と差別化の方向性が明確になります。
人間が1日かけて行うリサーチを、AIならわずか1分で終わらせることができるのです。
3-2. AIに「比較軸を作らせる」
多くの人が見落としがちなのは、「何をもって比較するか」という軸そのものの設計です。
競合分析は“情報の多さ”ではなく、“比較軸の正しさ”で決まります。
AIに次のような指示を出すと、自動的に比較軸を設計してくれます。
指示:この市場を分析する上で重要な比較軸を5つ挙げてください。出力例:
- 価格帯
- サービスの独自性
- 顧客体験の深さ
- 継続率(リピート率)
- コミュニティ・ブランド力
これをもとに再びAIに「各社をこの5軸で比較して」と追加すれば、
“競合表”ではなく“戦略マップ”として整理された分析資料が完成します。
3-3. 「自社優位性」をAIに整理させる
競合分析のゴールは、自社の勝ち筋を可視化することです。
AIに「この比較結果から自社の優位性を3つにまとめて」と伝えると、
AIは定性的な差別化要因をロジカルに抽出してくれます。
たとえば:
- 顧客体験の深さで差別化できる
- サブスクと体験イベントの組み合わせは他社にない
- コミュニティ形成が中長期のロイヤリティにつながる
このように「優位性の根拠」を具体的な言葉で整理できれば、
次章で扱う“論点整理”にスムーズに繋げられます。
3-4. 競合分析に使える万能プロンプト例
目的:自社の新しいオンライン学習サービスを企画したい。
条件:競合は3社(A社・B社・C社)、対象は社会人向け。
出力:各社の特徴・価格・強み・弱み・顧客層を比較表にし、
最後に「自社が勝てる戦略ポイント」を3つまとめてください。この1行だけで、AIは調査→比較→戦略整理までを自動で行います。
つまり、リサーチに費やしていた時間の多くを構想や戦略設計に回せるようになるのです。
4. 論点整理で企画を磨く
企画書の“完成度”を決めるのは、実は情報量ではありません。
最も重要なのは、論点が整理されているかどうかです。
同じ内容でも、論点が曖昧な企画は「何を伝えたいのか分からない」と感じられてしまいます。
逆に、論点が明確な企画書は、短くても印象に残り、説得力が段違いに高まります。
AIを使えば、この「論点整理」を短時間で正確に行うことが可能です。
人間の頭では追いきれない複数の視点を、AIが体系的にまとめてくれるからです。
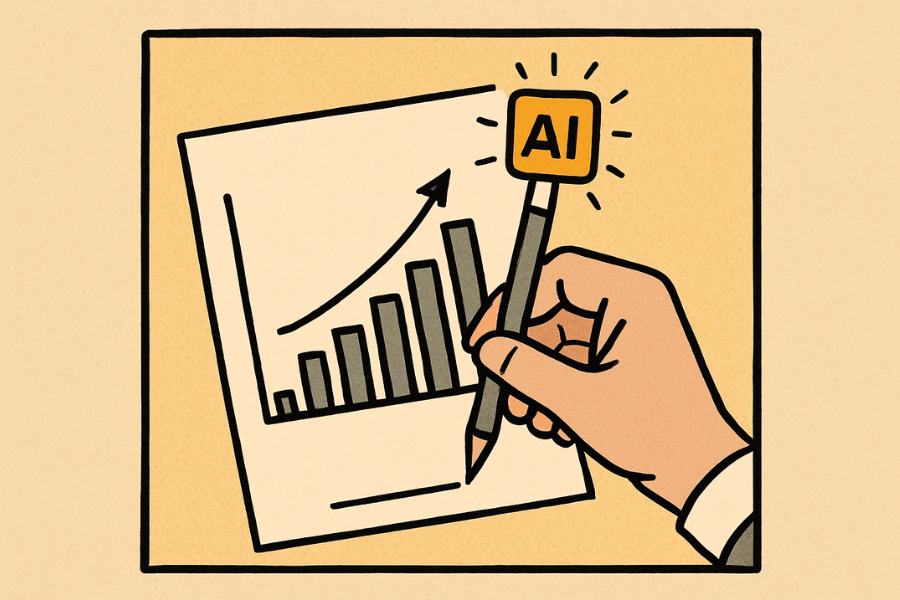
4-1. 論点とは「企画の主張を支える骨」
論点とは、企画書の主張を支える“柱”のようなものです。
例えば「新規顧客を増やしたい」という目的の裏には、次のような論点が隠れています。
- どの顧客層を狙うのか(ターゲティング)
- どんな価値を提供するのか(バリュープロポジション)
- どうやって認知・行動を促すのか(マーケティング戦略)
これらをAIに整理させることで、抜け漏れのない論理構造が生まれます。
4-2. AIで論点を自動抽出する方法
AIに次のように依頼してみてください。
テーマ:20代社会人向けの新しい読書サブスクを企画したい。
指示:このテーマを企画書にする際に考慮すべき主要な論点を5つ挙げ、それぞれの要点を100字以内で説明してください。AIが出す例:
- 市場性の確認:読書離れや電子書籍の普及など、ターゲット層の読書習慣を分析する。
- 提供価値の明確化:単なる本の提供ではなく、体験や学びにどうつなげるかを定義する。
- 価格モデルの検討:他サービスとの差別化を意識した柔軟な料金設計を行う。
- 継続率の向上策:読書を習慣化するための仕組みをどう設計するか。
- パートナー戦略:出版社・インフルエンサーなどの協業による拡張性を検討する。
これで、企画全体の思考の地図が一瞬で可視化されます。
この状態から構成を肉付けしていけば、ロジックの通った企画書が完成するのです。
4-3. AIで「抜け漏れチェック」をする
論点を整理したあとにAIへこう聞きます。
この企画において見落としている可能性のある論点を教えてください。するとAIは「コスト試算」「実証実験」「データの信頼性」など、
自分では思いつかなかった視点を補ってくれます。
この一手間で、企画の抜け漏れをゼロに近づけることができます。
4-4. 論点整理のプロンプト例まとめ
目的:AIで企画書の論点を整理したい。
条件:社内向け、経営陣に提出する資料。
出力:企画書を構成する主要論点を5〜7個に整理し、
各論点の要旨と検討すべきサブポイントを簡潔にまとめてください。このプロンプトを使えば、「考えを整える時間」から「企画を磨く時間」へシフトできます。
AIを使う最大の目的は、単に作業を効率化することではなく、
人間がより創造的な思考に集中できる状態をつくることなのです。
5. 上司を納得させる構成
どれだけ優れたアイデアでも、伝わらなければ存在しないのと同じです。
企画書の目的は「良い企画を出すこと」ではなく、「相手を動かすこと」。
そのためには、内容以上に“構成”が重要になります。
AIは、この「相手を動かす構成」づくりにも強力なサポートをしてくれます。
ここでは、上司が納得する企画書の順序・論理・見せ方をAIとともに組み立てる方法を紹介します。
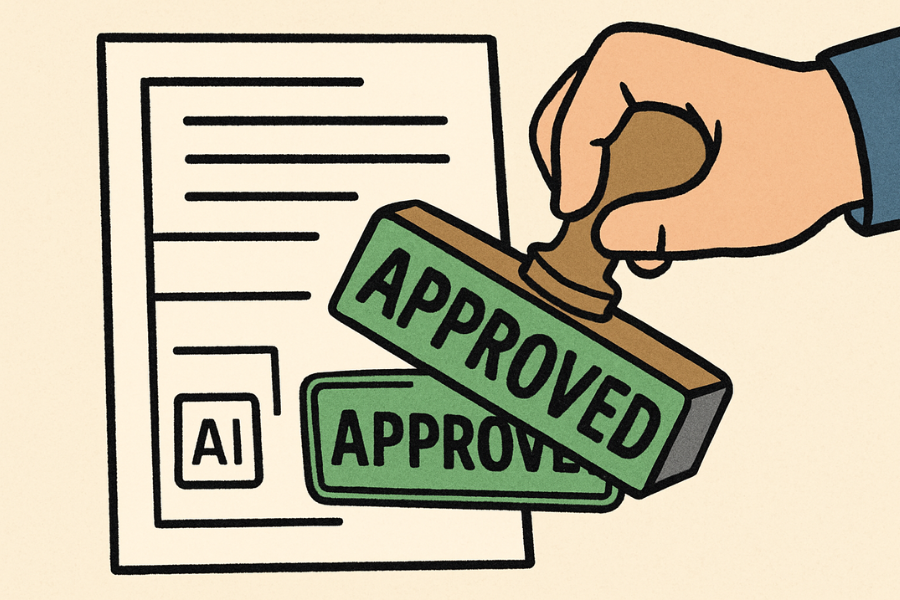
5-1. 上司は「論理」ではなく「ストーリー」で動く
上司は多忙です。
ページ数の多い企画書を隅々まで読む時間はありません。
にもかかわらず、多くの人は「データ」「背景」「課題」から延々と説明を始めてしまいます。
人は論理よりも「ストーリー」で理解します。
そのため、AIには次のように依頼して構成を設計させます。
指示:以下の要素をもとに、上司に一目で伝わる企画書のストーリー構成を提案してください。
条件:5〜6枚程度のスライド、結論ファーストで構成。
要素:目的、課題、解決策、効果、実行計画AIが出す典型的な構成例は次のとおりです:
- スライド1:結論(何を実現したいのか)
- スライド2:現状(なぜ今、この課題に取り組むのか)
- スライド3:課題の本質(放置すると何が起きるのか)
- スライド4:解決策(提案する具体的施策)
- スライド5:効果と展望(得られる成果)
- スライド6:実行ステップ・スケジュール
この構成のポイントは、最初の1枚で「結論」を伝えることです。
「最初に答えを見せて、理由をあとから補足する」。
これだけで、上司の理解度と信頼度が大きく変わります。
5-2. 「刺さる一文」をAIに作らせる
上司の心を動かすのは、数字ではなく“言葉”です。
企画書の中で最も重要な箇所は、タイトルと導入文の2行。
ここに魂がこもっていなければ、どんな分析も届きません。
AIを使えば、この“刺さる一文”を瞬時に生成できます。
例:
指示:この企画書のタイトル案を5つ提案してください。
条件:上司が会議で「これいいね」と言いたくなるようなキャッチコピー調で。出力例:
- 「離職ゼロのチームをつくる“1on1再設計プロジェクト”」
- 「たった5分の仕組みで生産性を10%上げる方法」
- 「AIが会議を変える──資料作成のムダをゼロに」
このようなタイトルをAIと共創することで、
自分では思いつかなかった表現に出会うことができます。
5-3. 説得力を「構成×ビジュアル」で補う
AIは、構成だけでなく図解や表現スタイルの提案にも優れています。
次のように頼むと、論理の流れを視覚的に整理してくれます。
指示:以下の内容をスライドで表現する場合の図解案を3パターン提示してください。
条件:上司が直感的に理解できるようなフロー図・ピラミッド図・対比表の形式で。AIが提案する例:
- フロー型(課題→施策→成果の流れ)
- ピラミッド型(最終目的を頂点に据えた構造)
- 対比型(現状と理想の差をビジュアルで示す)
構成が整理された資料ほど、説得力は増すものです。
AIに構成と見せ方を同時に設計させれば、企画書は「読ませる」から「見せて伝える」資料に進化します。
5-4. 上司を納得させるためのプロンプト例
最後に、構成づくりに役立つ万能プロンプトを紹介します。
目的:社内プレゼン用の企画書を作成したい。
条件:5枚構成で、上司が短時間で判断できる流れにしたい。
出力:論理構成(見出しタイトル・要約・図解案)をスライド順に整理してください。このプロンプトをベースに、生成された構成を肉付けしていくだけで、
「わかりやすい」×「通る」企画書が完成します。
AIを恐れず、“自分の頭の補助エンジン”として使うことが、
今後の企画力を大きく分けるポイントになります。
まとめ
企画書を「ゼロから作る時代」は、もう終わりを迎えています。
AIを活用すれば、骨子・論点・構成・表現のすべてを短時間で整えることができます。
AIは“代わりに考えてくれる道具”ではありません。
むしろ、人間の思考を深めるための鏡です。
AIに問いを投げるたび、自分の考えが明確になっていく感覚を得られるでしょう。
次に新しい企画を任されたとき、
「まずAIに骨子を出してもらおう」と思えた瞬間、もうそれは“AI時代の企画の第一歩”です。
今後の仕事のスピードも、成果も、確実に変わっていくはずです。